
都市経済の自立的成長
岡山大学経済学部 中村良平
1.都市成長の考え方
1.1 都市と人口
経済的な観点からすると、国レベルの成長は、GDP(国内総生産)の伸びで示されることが一般的である。これに対して、都市経済とか地域経済の成長は、しばしば人口の変化を指標として評価がなされる。つまり、人口が伸びている都市は成長している都市であり、減少しているのは衰退傾向にある都市とみなされる。これは、都市経済や地域経済が国民経済に比べて、開放性が極めて高いことに由来しているからである。つまり、都市経済の成長力が、開放性が高いがために、労働や資本といった生産要素の流入や流出といった移動に反映し、その帰着点が人口であるということを意味している。
この場合の都市とは、行政的な意味での自治体としての市ではなく、経済学的に定義される都市もしくは都市圏を意味している。しかしながら、現実の都市政策を考える場合には、「市」が都市と見なされる。すると、そこには、居住者としての常住人口と就業者や就学者としての昼間人口の間におのずから乖離が生じてくることになる。
図−1は、東京・愛知・京阪神の大都市圏に属する都市を除く県庁所在都市37のいわゆる地方の中核都市もしくは中枢都市と呼ばれる市について、国勢調査による1990年と1995年の間での常住人口の変化率と昼間人口の変化率の相関を示したものである。

第1象限にある都市は、常住人口も昼間人口も増加した都市であり、就業機会や就学機会の増加と同時に居住機会も向上している都市であることを表している。対象とした37の都市のほとんどがそれに該当しており、常住人口と昼間人口のどちらで見ても都市が成長していることを意味している。
ただし、双方の変化率が等しくなる45度線を境に、同じ成長といってもその解釈は異なってくる。45度線の上方部分に位置する都市は、居住機会が就業機会の増加を十分に賄いきれてない場合であり、経済的成長が生活都市としての成長を上回っていると解釈できよう。都市の発展段階仮説にしたがうと、成長期における相対的分散傾向を示している第3段階に位置しており、周辺市町村への郊外化現象が進展している状況を示唆している。 これには、対象都市の大多数(30都市)が該当している。これに対して、45度線の下方部分に位置しているのは、常住人口の伸び率が昼間人口の伸び率を多少とも上回っている都市であり、その都市が郊外化現象を呈していると解釈できるが、該当する都市の旭川市、鳥取市、松山市ではその上回り方は微少であり、昼夜バランスある成長と見ることが出来る。
第2象限に位置する都市は、昼間人口の増加に反して常住人口が減少しており、都市部の空洞化が懸念される都市である。これには、前橋市が該当しており、また岐阜市や和歌山市も第4象限にあるものの常住人口の減り方が昼間人口のそれを上回っている。
37の対象都市の中で、昼夜間人口ともに変化率がマイナスであったのは、岐阜市、和歌山市、長崎市の3都市であった。ただし、いずれの都市も就業者数では、常住地・従業地とも増加している。
表−1では、具体的な変化率の数値に加えて、1995年の昼夜間人口比率を示したものである。対象都市の全てにおいて、昼夜間人口比率は1.0を上回っている。昼夜間人口ともに成長率の高かった都市には、札幌市、仙台市、福岡市と3つの地方中枢都市が含まれており、それぞれ地域内の周辺市町村からの人口集中傾向が考えられる。旭川市や山口市も成長率は高いが、昼夜間人口比率は1.0に極めて近く、都市圏の中心都市としての成長というよりも居住地としての発展の方が感じられる。
 表−1 地方中核都市の人口特性
表−1 地方中核都市の人口特性
以上のように、地方中核都市には、人口側面からすると昼夜間において比較的バランスのとれた成長をしている都市が多くあると言えよう。
1.2 都市と経済
それでは、このような人口の変化は何によって規定されるのであろうか。昼間人口、より厳密には昼間就業者数(都市の従業者)が都市の経済力に応じて決まってくるものとすると、それは都市の実質総生産額の変化が労働需要に対して影響を与える因果関係が考えられる。もちろん、生産要素は労働だけではなく、土地も含めた有形固定資本も存在する。したがって、実質生産額が増加しても、技術進歩が資本との代替関係を促すようであれば、労働需要はそれほど増加しない。また、労働の質が高まれば、より少ない労働力で生産力を維持することができることになる。
図−2は、1990年から95年までの都市の製造業(工業)について、従業者数の変化率を横軸に縦軸を付加価値額の変化率にして、地方中核都市名をプロットしたものである。
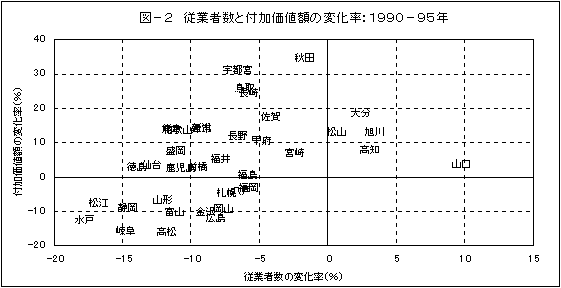
これによると、半数以上の都市について付加価値額が増加しているのに対して、従業者数も増加しているのはわずか5都市となっている。付加価値額の増減には、事業所数の増減も関係するが、都市全体として工業生産力をとらえる場合には、変化率がマイナスであれば、生産力は低下していると判断できよう。また、45度線の上方に位置する都市は、付加価値額の変化率が従業者の変化率を上回っている都市であり、そこには労働生産性の高まりが考えられる。
そこで図−3では、横軸に資本労働比率の変化率をとり、縦軸に労働生産性の変化率をとったものをプロットした。 これによって、事業所数の増減の影響はコントロ−ルできたことになる。

既に述べたように、労働生産性の向上はリストラによる人員削減効果も多く含まれているが、その場合に労働から資本への生産要素間の代替が生じていることが考えられる。図−3の散布図の状況から、若干の都市を除いてその傾向が見受けられる。また、資本労働比率の変化率については、資本分配率の平均値をそれに乗じていることから、図の45度線の上方にある都市ほど、労働生産性に対して技術進歩の貢献度が大きかった都市であると考えられる。
このように都市の経済力を製造業で見ることはその一面を見ているにすぎず、むしろ地方中核都市の場合には、都市経済に対して非製造業の果たす役割が基盤産業として大きいと考えられる。実際、図−4で見るように、工業生産力の変化と昼間人口の変化の間には、強い相関が見受けられないのが実状である。

次節では、都市経済力の向上について需要と供給の面に分けて、その成長の原動力を考えてみる。
2.都市経済力の向上
都市の経済力が高まることは、言い換えると、経済力の指標である生産額(付加価値額)が大きくなることを意味している。前節で示した工業生産額もその一要素である。そして、この中身には2通りある。1つは、既存の企業や産業がそれらの生産額を伸ばすことである。もう1つは、新たな企業や産業が域外から立地したり、都市内で生まれ、それによって都市全体の生産額が増加する場合である。特に、後者については、経済低迷が長引くなかでの新規産業の経済に対して果たす役割とその必要性が言われて久しい。
2.1 既存産業の高度化
既に都市に立地している企業や産業の生産額(あるいは販売額)が増加する理由には、企業や産業にとって受動的な要因と能動的な要因とがある。
たとえば、所得税減税による個人の実質可処分所得の高まりなど、消費意欲の拡大によって生産額(販売額)が増加したとしよう。これは受動的な成長であって、次節で示す需要主導型の都市経済成長の典型である。また、当該都市が出荷している財・サ−ビスについて、それと競合している他都市の価格が何らかの事情で上昇し、相対的に優位に立ったとしよう。これによって、当該都市の移出額が伸び、生産が拡大する場合も受動的な理由と見なされる。
これに対して、能動的な要因とは、たとえば、積極的な研究開発投資を行った結果の技術進歩による新製品の創出である。これは、次にも述べるような新規産業としてしばしば成長することもある。また、企業が都市内外の需要に応じた生産を積極的に展開したことによる成果の場合もある。もちろん、この場合は、それらが市場の潜在的需要を喚起していることが必要条件である。
既存産業の高度化とは、このような生産額の拡大が対投入要素の効率性において達成されることを意味する。すなわち、労働生産性や資本生産性の向上である。
前者の労働生産性の向上は、その分子である生産額の増加と分母である労働の省力化の相対関係によって達成される。研究開発投資をおこなうことは、実証分析の前提において、しばしば資本と労働に中立的な技術進歩を導くとされる。この技術進歩の中身は、資本設備の質を高め、同時に高い労働の質を必要とする。したがって、これが労働生産性を結果的に高めることになる。
単純なリストラによって労働生産性を高めることは、社会的に余剰労働力を生み出し、しばしば高い失業率となって現れる。真の労働生産性の高まりとは、労働と資本設備の質を同時に高めることによって達成されることが望ましい。これを考慮した官民の投資が既存産業の高度化に結びつくのである。
2.2 新産業創出の意味
21世紀を間近にひかえ、通商産業省「産業構造審議会総合部会基本問題小委員会」では、これから有望な産業分野として、情報・通信分野、医療・福祉分野、生活文化関連分野など15の分野が掲げられている。これら有望な分野においては、当然新たな産業の創出が期待される。
都市経済の発展や成長にとっても原動力となるのが都市型産業、しかも新規産業の育成であることについては議論の余地はないであろう。
それでは、このような有望分野における新産業の創出の意味をどのように整理すれば良いであろうか。経済学的に考えると、それは需要と供給といった2つの側面からとらえることができる。
1つは、従来未知であったことに対する発見や新たな発明によって、それを利用する技術が生まれ、製品化され、そして商品化(市場化)される場合である。この代表例としては、遺伝子構造の発見(解明)や半導体の発明などがあげられる。これらの発見や発明が、実用化に向けての長い試行錯誤の期間を経て、バイオ関連分野の産業やハイテク関連分野の産業として成長をとげ、また今日より大きな発展が期待されている。これは、生産における技術進歩という意味で、供給主導型で生まれる産業(業種)分野である。また、これが社会における新たな需要を創出している。
もう1つは、時代の必要性あるいは要請によって生まれてくる産業分野とか業種である。たとえば、廃棄物リサイクルや地球温暖化といった社会問題が生じて、リサイクル技術の開発や環境保全システムの向上が必要となってくる場合である。あるいは、高齢化社会が進展する中で高齢者に対する様々なサ−ビス需要に応じる必要性が社会的に生じてくるといった場合である。これは、社会における既存技術の応用やシステムの改変で対応できる場合が多く、社会の需要という意味で、需要主導型で生まれる新規産業分野あるいは業種としてとらえられよう。もちろん、社会的需要によって、新技術が生まれることも大いにある。
3.都市経済の成長理論
本節では、これまで述べた都市経済の成長の定性的な考え方も含めて、都市成長の理論をモデルによって明らかにする。
3.1 生産市場における需要
都市経済における生産物市場の需要が果たす役割を見るために単純なモデルを考える。この場合の需要とは、都市が生み出す財・サ−ビスに対する都市内・都市外からの需要を意味する。また、生産財については、最終消費財のみならず、他の企業が需要する中間生産物(中間投入物)も含むものとする。
いま、都市レベルでの産業連関表が存在することを仮定すると、そこにおける最終行での各列間の関係式は、都市jにおける総産出額(![]() )、都市j内の中間需要(
)、都市j内の中間需要(![]() )、民間消費(
)、民間消費(![]() )、民間投資(
)、民間投資(![]() )、公的支出(
)、公的支出(![]() )、輸移出(
)、輸移出(![]() )、輸移入(
)、輸移入(![]() )を用いて、
)を用いて、
(1) ![]()
と表すことができる。ここで、変数の上に「−」のある公的支出(![]() )と輸移出(
)と輸移出(![]() )は、当面、都市jにとっての外生変数としてとらえておく。
)は、当面、都市jにとっての外生変数としてとらえておく。
伝統的なケインズ型の所得決定モデルだと(1)式は、付加価値ベ−スで
(2) 
と表現される。ここで、![]() は都市jにおける総生産額であり、同時に都市jにおいて発生した付加価値額の合計でもある。(2)式の右辺は都市j内から発生した最終総需要(
は都市jにおける総生産額であり、同時に都市jにおいて発生した付加価値額の合計でもある。(2)式の右辺は都市j内から発生した最終総需要(![]() )からその需要に応じて都市内では賄うことのできない部分が輸移入(
)からその需要に応じて都市内では賄うことのできない部分が輸移入(![]() )として控除され、さらに都市j以外の地域で都市jに対して発生した需要(
)として控除され、さらに都市j以外の地域で都市jに対して発生した需要(![]() )が輸移出として加わり、これに対応して都市での総生産(
)が輸移出として加わり、これに対応して都市での総生産(![]() )がなされるといった需要側からの恒等式を意味している。さらに、(2)式では、総生産額は都市jのなかで完全に分配され、生産所得(
)がなされるといった需要側からの恒等式を意味している。さらに、(2)式では、総生産額は都市jのなかで完全に分配され、生産所得(![]() )は分配所得に等しいと仮定している。
)は分配所得に等しいと仮定している。
まず、都市内でなされる民間消費については、統計上は明示的に現れることはないが、域外からの観光客の消費支出(交通費、宿泊費、飲食費、土産代)や買い物客の消費支出などが含まれている。これは、財の流れとしては移出であり、資金の流れとしては流入となる。すなわち、都市jにおける民間消費支出は、域内の消費者の消費額(![]() )と域外居住者の消費額(
)と域外居住者の消費額(![]() )との合計として、
)との合計として、
(3) ![]()
と表現できる。それぞれの消費額については、
(4) ![]()
(5) ![]()
のような線形関数を仮定する。ここで、他地域からの消費流入額を説明する![]() は地域jへの(訪問)消費魅力度であり、具体的には、商業集積の多様性、観光資源の質と量の指標が考えられる。
は地域jへの(訪問)消費魅力度であり、具体的には、商業集積の多様性、観光資源の質と量の指標が考えられる。
民間投資については、域外の企業の立地に先立つ用地取得やその後の建物などの建築投資や設備投資などは、投資資材をどの程度域内から調達できるかどうかにも関わるが、いずれにしても域内での固定資本形成に伴う資金の地域内への流入となる。
したがって、地域jへの投資に関しても消費と同様に、域内企業の投資(![]() )と域外企業の地域jへの投資(
)と域外企業の地域jへの投資(![]() )に分けて考える。すなわち、
)に分けて考える。すなわち、
(6) ![]()
となる。それぞれの投資額の要因についても民間消費額と同様の考え方で、都市内企業については所得で、また域外からの投資については、当該都市の投資魅力度(![]() )で説明できよう。
)で説明できよう。
(7) ![]()
(8) ![]()
輸移入については、
(9) ![]()
と仮定する。ここで、![]() はそれぞれの需要項目に応じた輸移入の比率を表す係数である。
はそれぞれの需要項目に応じた輸移入の比率を表す係数である。
(2)−(9)式の8本の連立方程式を解いて、それぞれの外生的変数の変化が与える効果度を示す乗数値の形で表現すると、公的支出が![]() 単位変化したとき、都市jの総生産額(=総所得)の変化は
単位変化したとき、都市jの総生産額(=総所得)の変化は
(10) 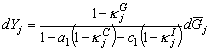
となり、以下同様に、輸移出額の変化に対しては
(11) 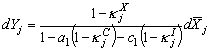
都市の消費魅力度の変化(![]() )については、
)については、
(12) 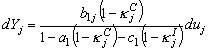
都市の投資魅力との変化(![]() )については
)については
(13) 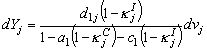
となる。
このようなケインズ型の需要決定モデルを想定すると、都市の経済力の成長に及ぼす影響において、公的支出と輸移出の違いは、それぞれの域外からの移入性向の単純な大小関係にのみ依存することになる。ただし、公的支出は市場メカニズムによらない都市経済にとっての受け身の変数であるのに対して、輸移出は都市経済の自己努力を必要とする能動的変数である。
したがって、輸移出をいかに拡大し創出するかについては、供給の側面を考慮に入れることが重要となってくる。
3.2 生産市場における供給
![]() で与えられる移出製品の出荷額は、域外の需要に依存することもさることながら、むしろ、域外の需要を喚起(あるいは創出)するような製品やサ−ビスを生み出すことが当該都市にとってより重要である。このことは都市経済の成長を供給サイドで考えることを意味し、
で与えられる移出製品の出荷額は、域外の需要に依存することもさることながら、むしろ、域外の需要を喚起(あるいは創出)するような製品やサ−ビスを生み出すことが当該都市にとってより重要である。このことは都市経済の成長を供給サイドで考えることを意味し、
(14) ![]()
という生産関数を想定することになる。ここで、![]() は技術進歩を高めるような変数であり、
は技術進歩を高めるような変数であり、![]() は資本ストックの質、
は資本ストックの質、![]() は労働の質を意味している。
は労働の質を意味している。
地域にとっての移出は外需といえども、地域の自立的発展には移出産業の創出と育成が欠かせない。新規産業の創出とは、まさに地域独自の新たな移出産業を生み出すことであり、そのために、伝統産業や地場産業の資源やノウハウを活かし、それらの連関を保つことが重要と思われる。
設備機器の更新や新規開発、労働の質の高まり、さらに中立的な技術進歩によって、移出産業の生産額の伸びは以下のようになる。
(15) 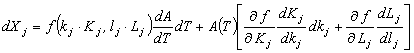
地域にとって、移出産業の就業者や資本ストックを識別するのは困難であるが、製造企業に限定して、実証分析が行える。公共支出に直接依存しない移出産業の育成の効果は、都市産業を活性化させる大きな原動力となっている。
3.3 要素市場における需給
都市の成長指標に人口の変化が評価として採用される理由については、第1節で述べたが、人口の構成要素である就業者については、都市の生産要素市場で考える必要がある。
要素市場における労働需要については、資本労働比率や技術進歩、さらに賃金水準などが影響を与えることがわかる。しかし、都市への労働供給については、都市への居住を考えると、賃金や物価水準に加えて、その都市の住環境や社会資本ストックの充実度が重要な変数となってくる。すると、都市jへの労働供給は
(16) ![]()
のような定式化が考えられる。ここで、![]() は都市jで得られる賃金、
は都市jで得られる賃金、![]() は住宅価格も含んだ都市jにおける消費者物価水準、そして、
は住宅価格も含んだ都市jにおける消費者物価水準、そして、![]() は都市jにおける社会資本ストックである。この
は都市jにおける社会資本ストックである。この![]() については、下水道整備率とか一人当たり公園面積のような数量で示す場合と先の公的支出
については、下水道整備率とか一人当たり公園面積のような数量で示す場合と先の公的支出![]() の実質的な累積投資額で示す場合が考えられる。最も望ましい表し方は、質を考慮した金額表示である。また、他都市との比較で考えるならば、右辺の説明変数は他都市あるいは全国平均値との相対変数となる。
の実質的な累積投資額で示す場合が考えられる。最も望ましい表し方は、質を考慮した金額表示である。また、他都市との比較で考えるならば、右辺の説明変数は他都市あるいは全国平均値との相対変数となる。
このことから、労働需要が増加しても常住人口が増加しないといった都市では、実質賃金が高くても、その効用をうち消す程度の定住環境整備の不足が内在しており、それらが相殺してしまっている状況と判断できよう。
4.都市経済の自立
4.1 自立の概念
3節のモデルに基づくと、都市や地域が自立的に成長するには、その都市が他の地域や海外からの需要を顕在化させるような移出品を持続的に生み出すことが必要となってくる。これは、果物や野菜などの農産物や従来の工業生産物のような目に見えるものだけには限らない。情報発信、ファッション、知識、技術など他の地域で考えられていないようなもので、従来はソフト産業やサ−ビス産業にまとめられている分野もそうである。アウトプットとして具体化される前の段階のもので、そこから萌芽的なアイディアが生まれてくるようなものが重要である。
都市にとっての移出産業は別名、基盤産業とも呼ばれている。それは、移出産業の盛衰が地域の発展の基盤になるからである。基盤産業は域内の需要のみならず域外からの需要によっても成り立っている。そうすると基盤産業は外需依存型とも考えられるが、その外需を顕在化させて地域にとっての需要とするのが真の基盤産業である。これに対して、地域内の需要によって成り立つ派生産業は域内産業と呼ばれる。建設業、小売店、地域の金融機関や域内交通などがその典型例である。地域の個人や企業を対象としたサ−ビス業もそうであろう。
従来の考えでは、サ−ビス業は、一次産業や三次産業に付随して発生し、ロ−カルな需要を満たすものであった。しかしながら、高度に情報化した社会において多様化するサ−ビス産業の中には、移出産業も数多く現れている。東京に集積するシンクタンクや情報関連サ−ビスなどはその典型である。そして、それらが生まれるには、猥雑で雑多なところも必要だが、頻繁なフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケ−ションが可能な交流の場と機会がいると考えられる。
内需である公共投資は、周知の乗数効果によって地域所得を高めると同時に、直接的な雇用効果も産みだすことから、景気回復策として、今なおそれに依存する状況が根強い。
3.1で見たように、この乗数効果の高さは、1つは限界消費性向の高さに依存する。すなわち、貯蓄性向の低い県民性の地域は、公共投資の効果が消費増加をより高くある。もう1つは、地域経済の閉鎖性である。あるいは、自給性の高さである。公共投資に派生する域内での資材調達率が高いほど、域内の乗数効果は高まることになる。
一国レベルでの公共投資の効果は所得効果に力点が置かれるが、地域にとっては直接効果としての雇用効果を期待する傾向が強い。しかし、ある公共事業が終われば、雇用効果は消滅し、逆に失業率が上昇することになる。その結果、小規模の自治体の首長ほど、公共事業に依存することになり、公共事業が地域経済に対してカンフル剤からモルヒネに変化し、中毒症状を起こす結果となる。
地方の都市経済が公共投資依存体質からどのように脱却するか。これには、モデルからも明らかなように消費と投資の域内への流入と移出産業を育成することが必要となる。
4.2 財政の自立性
地方自治体としての都市の自立性を見る場合に、最も重要な指標は財政指標である。地方財政の面での自立性とは、1つに一般会計に占める自主財源の割合が高いことが挙げられる。具体的には、歳入総額に占める地方税、財産収入、手数料・使用料、分担金などの割合である。この割合が高い方が、財政運営において自主性や主体性が発揮しやすいことになり、財政的な自立度を表している。もう1つは、行政サ−ビスに必要な額、すなわち基準財政需要額に対する税収や地方譲与税などの基準財政収入額の割合である。基準財政需要額が収入額を上回っていれば、地方交付税の対象自治体となる。
図−5は、自主財源比率を横軸にし、縦軸を基準財政需要額に対する収入額の比をとったものである。
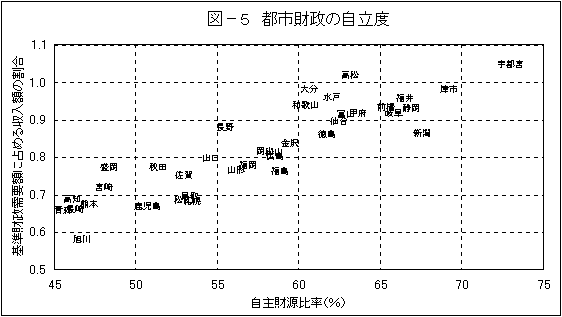
地方財源における2割・3割自治が指摘される中で、対象とした37の地方中核都市では、自主財源比率が全て45%を超えており、それほど自立性が低いとは言えない。しかし、財政需要の面から見ると、基準財政収入が需要額を上回っている都市は、わずか2都市にすぎず、ほかの地方中核都市はすべて地方交付税の交付団体となっている。これとの自主財源比率との相関も極めて高く、都市財政の自立性を高めるにはより一層の自主財源を充実させる施策が必要となってくる。
4.3 産業の自立性
自立した都市経済とは、基盤産業としての移出産業を十分に有していることである。この移出部門を如何にして識別するかは重要であり、また非常に困難でもある。従来から、移出産業の識別には立地係数(
Location Quotient)もしくは特化係数を用いた評価が行われてきた。 ある時点での都市jにおける産業iの就業者数を![]() とすると、就業者で表現した都市jにおける産業iの立地係数もしくは特化係数(
とすると、就業者で表現した都市jにおける産業iの立地係数もしくは特化係数(![]() )は、
)は、
(17)
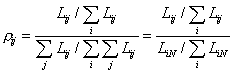
と定義できる。ここで、分母は全国レベルにおける産業iの就業者の割合であり、それが各都市の産業iに関する特化係数の基準となっている。
図−6aとbは、1996年の事業所統計を用いて、昼間人口が50万人を超えている都市について特化係数をグラフ化したものである。またグラフでは、都市型産業として成長が期待される情報発信に関係する業種について示している。
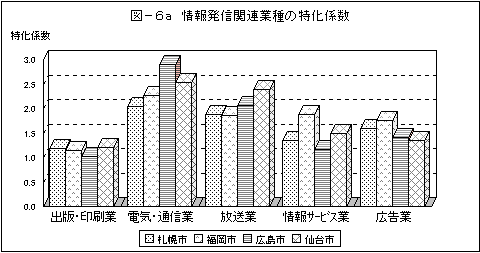
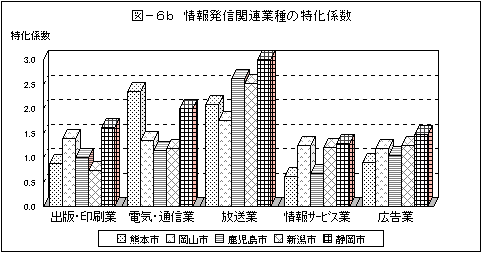
5つの業種の内、出版・印刷業のみが製造業であり、熊本市や新潟市などでは特化係数が1.0を少し下回っているが、静岡市や岡山市などでは1.5前後と都市の基盤産業と見なせよう。電気・通信業に関しては、対象9都市で全てが1.0を上回っており、中でも4つの地方中枢都市では全国平均の2倍の集積度を示していることがわかる。放送業では、中枢都市よりも鹿児島市や新潟市、静岡市といった地方中核都市の方が高い集積度を示しており、これらの都市では情報発信産業としての基盤産業となっていると考えられる。しかし、同様の情報発信機能としての広告業については、中枢都市に比べて地方中核都市において基盤産業とは十分になり得ていないと言えよう。情報サ−ビス業では、4つの地方中枢都市と5つの地方中核都市の間では格差が生じている。なかでも熊本市と鹿児島市では低い特化度となっており、都市の基盤産業とはなっていないことがうかがえる。
5.地方中核都市の課題と役割
5.1 都市内交流と連携
多くの地方中核都市は、支店経済として発展してきた。そこには、金融・保険関係の事業所や公的機関の集積、また関連するサ−ビス業の一定の集積を見ることができる。このことは、いわゆる都市集積の経済性を享受できる基盤が備わっていることを意味している。さらに、都市圏域の周辺市町村も含んで考えると、そこには伝統的な地域の地場産業や基盤産業も多く存在している。
自立的な経済を達成するには、この都市集積の効果を生かした都市圏域内における同業種・異業種を問わない交流がまず必要である。これは、都市内における産業連関を密接にするためにも重要なことである。直接対面することによるフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケ−ションという交流手段によって新たなアイディアや企画が生まれる可能性は高い。
当然、同業種間においては競争意識も働くことが予想される。しかし、シリコンバレ−で知られるカリフォルニアのサンノゼ周辺地域においては同業種交流によって、都市活力を生み出していることは良く知られている。実際、競争のない連携は、相互もたれ合いの関係に陥り、新たなものが生まれてくる可能性は低くなる。また、異なる産業間の交流は、物づくりから企画、商品開発、マ−ケティングにいたるト−タルとしての6次産業化を進める。
これらの「場」は、民間主導で形成されるべきであるが、行政がその「場」や「機会」を作り出すというアシストをおこなうことも考えられる。ハ―ド面での助成やソフト面での補助金も必要であるが、何よりもそういった交流の場に行政も積極的に参加することである。これが、都市産業のインキュベ−タ(孵卵)として機能する。
このことは、3.2の(14)式における![]() の
の![]() の部分を大きくすることを意味している。
の部分を大きくすることを意味している。
5.2 都市間交流と連携
中四国地域でみると、高速道路網の整備や大型交通インフラである瀬戸大橋や明石海峡大橋の完成、間近に迫った尾道〜今治ル−トの開通などで都市間の利便性が高まってくる。さらに、各県が進めている高度情報化推進施策による地域間連携も始まりつつある。これらは中国四国地域の拠点性を高めると期待されている。このことは中四国地域の都市に限らず、全国の地方都市について当てはまることである。
しかし、交通インフラの整備は、地方都市にとって両刃(もろは)の剣である。例えば、1988年に瀬戸大橋によって四国と本州が陸路で結ばれたことによって、本四間の交流は一躍活性化した。ところが四国の玄関口であった高松市にとっては、瀬戸大橋が西の坂出に架かったこともあって、いわゆる「築港」としてのタ−ミナル機能が低下した。1991年から96年にかけて事業所数の変化を見ると、全国では0.55%減少しているが、高松市では0.59%減少と全国値をわずかではあるが上回っている。本四とのアクセス条件が改善されたとはいえ、松山市においても1.76%の減少を示しており、(対岸の岡山市は2.91%増)、四国における中核都市の支店経済力の低下が現れている。
拠点性の向上には、営業所経済や支店経済に依存した経済構造から、新たな産業を生み出すインキュベ−タ型の都市経済構造へ転換する必要がある。それには、都市内の企業間交流に基づく連携のみならず、高速交通インフラや高度情報インフラを利用した都市間・地域間の交流と連携が必要となってくる。
大学や公的機関の研究施設を相互利用することによる新たな技術や製品開発といった供給主導型のみならず、高度情報システムを用いた人材情報の交流によって労働需要の受給ギャップを解消させる可能性もある。さらに、交流によって各地の地場産業の成功事例やそのノウハウを得ることもできる。
また、都市間の連携によって域外からの消費や投資を呼び込むことも考えられる。もちろん、この前提には都市間競争があることから、3.1における(5)式の![]() や(8)式の
や(8)式の![]() を高めるための政策努力が必要となってくる。このとき、誤った過当競争による過剰投資も懸念されるが、それには地域連携が歯止めの役割を果たさねばならない。
を高めるための政策努力が必要となってくる。このとき、誤った過当競争による過剰投資も懸念されるが、それには地域連携が歯止めの役割を果たさねばならない。
都市間や地域間の財やサ−ビスの交流(移出・移入)といった循環は、3.1節で示した単一都市の乗数モデルを複数都市間の相互関係モデルに概念を発展させる。このとき、ある都市における移出は他の都市の移入となり、その逆も存在する。都市間の財・サ−ビスの循環構造は、明らかに移出乗数(11)の値を大きくすることになる。さらに生産要素である労働や情報の交流は、都市の移出を安定させる機能を持っている。
都市経済の自立的成長は、競争意識を忘れない形での都市内における人と情報の対面交流と連携、そして、それを社会的共通資本である高速道路や高度情報施設を活用して、都市間に広げることで財やサ−ビス、人と情報などの循環構造を形成することによって可能となろう。
景気のいいときには、ものは作れば売れるといった状況であったが、今日のように景気が長く低迷しているときには、それではダメで需要を喚起しないといけない。公共投資のような伝統的な景気刺激策だけでなく、交流に端を発したイノベ−ションによって新しいものを都市が生み出し、他の地域や海外からの需要を顕在化させる必要があるし、またそういったところへの公共投資が補完的役割として重要になってくる。1つでもそういった都市が現れると、波及効果によって他の都市へ伝搬し、全体として経済の活性化につながる可能性がある。
<補足>
経済基盤モデルの展開伝統的な経済基盤仮説に基づくモデルでは、産業を域内需要部門と輸移出部門に分けるといった二分法によっている。これを産出額で表現すると
(A1) ![]()
となる。ここで、輸移出部門の産出額(![]() )が基盤産業部門の産出額、域内需要部門の産出額(
)が基盤産業部門の産出額、域内需要部門の産出額(![]() )が非基盤産業部門の産出額と定義される。
)が非基盤産業部門の産出額と定義される。
次に、非基盤部門の産出額が都市の総産出額の一定割合(![]() )である、すなわち、
)である、すなわち、
(A2) 
であると仮定することによって、基盤産業部門変化に関する都市の総産出額の影響、換言すると移出乗数値を
(A3) ![]()
と導いている。
しかしながら、(A1)式は(1)式と比較してわかるように、経済基盤モデルでは都市jの自給経済を前提にしている。 そこで、改めて自給経済の産出額を![]() とすると、(A1)式は
とすると、(A1)式は
(A4) ![]()
と書き改められる。ところが現実の都市経済は自給ではなく輸移入もあり、自給経済であるためには輸移入も考慮する必要がある。これは
(A5) ![]()
と表せる。(A4)と(A5)から、
(A6) ![]()
が得られ、(1)式に対応した関係式が導ける。
ここで2.1と同様な仮定で、非基盤部門の生産需要と輸移入の需要を
(A7) ![]()
(A8) ![]()
と表す。ここで、![]() と
と![]() は、それぞれの需要に対応する限界需要パラメ−タである。
は、それぞれの需要に対応する限界需要パラメ−タである。
(A5)-(A8)式より、都市jの産出額は都市にとっての外生変数である輸移出を説明変数とした
(A9) 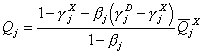
のようにモデルが解かれ、![]() にかかっている係数が輸移出乗数と解釈される。
にかかっている係数が輸移出乗数と解釈される。
参考文献
中村良平『いま都市が選ばれる−競争と連携の時代へ』、山陽新聞社、1995年
中村良平・田渕隆俊『都市と地域の経済学』、有斐閣ブックス、1996年.
中村良平「移出乗数と都市成長」、応用地域学会、1997年.
中村良平「新産業の創出と四国産業の高度化に向けて」、ルネサンス四国(四国電力)、1998年.