| 解説 | ||||
| Katsura T., Funakoshi K., Kubo A., Nishiyama N., Tange Y., Sueda Y., Kubo Y., Utsumi W., A large-volume high-Pressure and high-temperature apparatus for in situ X-ray observation, 'SPEED-Mk.II', Phys. Earth Planet. Inter., 143-144, 497--506, 2004. | 戻る | Full text | ||
|
新しい超高圧高温その場X線観察装置 'SPEED-Mk.II' の開発 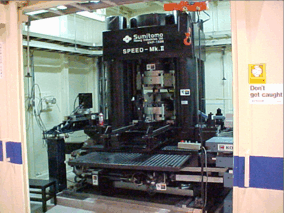 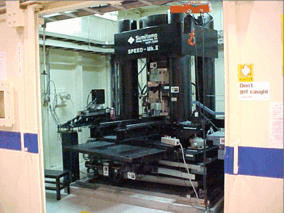 図1 SPEED-Mk.IIによる揺動機構。総重量20トンの超高圧発生装置は、鉛直軸(κ軸と呼んでいる)周りに20度回転する。左の図はκ=-7°、右の図はκ=13°の位置で撮影したもの。 この揺動機構の威力は絶大です。まず、下の図はMgOの800℃での回折パターンです。この温度では、粒成長はしていません。  次の図は、1800℃での回折パターンです。多くの回折線が消失していることが分かります。  これを揺動させると、次の図のように多数の回折線が復活します。 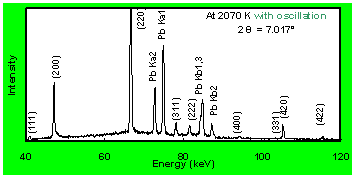 揺動機構を用いれば、高温でも良質の回折パターンを取得することが出来ることが分かります。 このように、SPEED-Mk.IIにより、大型高温高圧X線回折の温度圧力範囲を、大幅に拡大することが出来るようになりました。 |
||||
| top | メンバー | 研究方針 | 学生の方々へ | 設備 | 業績 | レビュー | リンク |